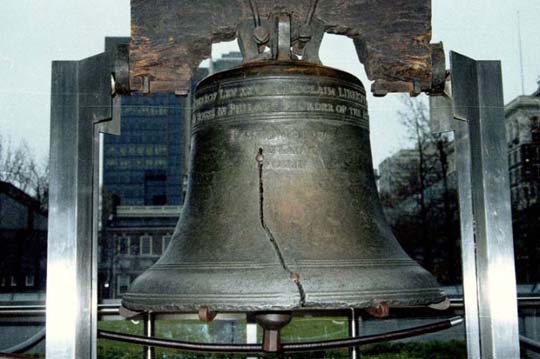「米国50州雑記帳」は1994年に全50州を踏破した折に作った冊子を再録しているのだが、50州の中には仕事がらみの話が少なくない。仕事の昔話は仲間内では懐かしくても、部外者には興ざめな「楽屋話」でしかない(老人の回顧譚に辟易とした経験は誰にもある筈)。会社員の守秘義務が死ぬまで消えないことも承知だが、半世紀前の小生のニューヨークでの体験は、米国の内情を知る上で参考になると思うので、例外の「楽屋話」をお許しいただきたい。
米国人は、自分にとって価値のある商品と認めれば、何処の誰が作ったのかにはこだわらない。米国製品に世界一の価値があれば米国製を愛用するが、外国製の方が優れていれば躊躇なく外国製を買う。そうなると市場原理が敏感に働く米国では、国内産業がアッという間に頓死に至る。その最初が綿繊維製品で、米国の繊維産業は1960年代に日本からの輸入品で壊滅した。これに家電と自動車が続き、更に鉄鋼、コンピューター、半導体にまで同様の状況が出現して、まさに米国の「お家芸」を次々と日本が奪い取るかたちになった。1980年代の米国は「自由市場」の旗印をかなぐり捨て、日本製品の輸入規制と米国製品の日本市場への「政治的押し売り」に走ることになる。
その頃小生が営業役で関わった商品は電話局間を繋ぐ通信幹線用の装置で、1台数百万円、一式の契約額は数億円になった。世界最先端の技術王国である米国は、通信機器も自給自足してきたのだが、日本製が「価値ある商品」になった背景には、「資本主義王国」米国ならではの事情があった。当時の米国は国内通信網が完成し、電話局用機器の需要はピークを過ぎていた。通信機の規格が世界標準と異なる米国は、輸出努力も無きに等しい。そうなると通信機産業は「斜陽」と見做され、技術者や設備はさっさとリストラされてしまう(それが経営者の仕事)。新たな需要が見込めればまた工場を建て技術者を集めるのだが、即利益が期待できなければ投資は起きない。当時は通信網がアナログからデジタルへ転換する兆しが見えていたが、米国の通信機業界はまだ休眠していた。そんな時、当社が新型デジタル通信機の実証試験レポートを英文技術誌に載せたところ、ニューヨーク電話会社の技術者が「待ってました!」とばかり飛びついたのである。
電話会社の技術者には他社の同職者と横の情報ネットワークがあり、当社機器の信頼性が高い(故障しない)ことが伝わって芋づる式に受注が拡がった。海外メーカーの新技術で取引額が数億円となれば、買い手が身構えても不思議はないのだが、どの電話会社でも「主任クラス」の担当技術者が万事取り仕切り、売り手側は接待攻勢やエライさんの顔合わせなど「あの手この手」の営業活動を繰り出す要もなかった。「営業」の仕事は先方が必要とする技術情報を迅速に提供することに尽き、文系の小生も「習わぬ経を読む」内に、いっぱしのエンジニア気分になったものである。
小生が接した客先の技術者は例外なく好意的で、かわいがってもらった記憶しかない。その時は気にもしなかったのだが、後になって「もしかして?」と思ったことがある、彼等がイタリア系、ドイツ系など、米国の白人社会では「亜流」とされる血筋の人たちばかりだったのだ(中には先住民(インデイアン)酋長の末裔もいた)。逆に難攻不落で剣もホロロだった客先では、担当がWASP(本流の英国系)だったケースが多く、第二次大戦の「日独伊三国同盟」がこんなところで復活する筈もないが、ある種のシンパシーが皆無だったとは言い切れない気がする(万年下積みの鬱屈を日本製品採用で晴らす気分もあったかもしれない)。電話会社の幹部は殆どがWASPだが、部下の仕事にモンクをつける余地がなければ恣意的に捻じ曲げることはない。それだけに、当社も客先担当の顔にドロを塗るようなミスは許されなかった。
米国は「人種のるつぼ」と言われるが、白人の間でさえ融合していないことは、現地社会に足を突っ込めば見えてくる。小生が後年現地社員の人事に関わった折、人事担当(北欧系白人)が折にふれヒソヒソとレクチャーしてくれた(公に口にできないのでヒソヒソ話になり、名前や顔つきで血筋を推定する秘訣も教えられた)。マイノリティ(白人以外、女性)の処遇は公的ルールに則って対処すれば問題は起きないが、白人間の民族問題は話題にしてはならないタブーである。しかしこの問題に無神経に人事を行うと、組織の人間関係をジクジクと蝕んで破綻に至ることがある。「ウマが合わない」のは、個性の衝突よりも、背後に民族的な反目が隠れている場合が少なくないのだ。
白人間の民族問題とは、英国系(WASP)、北欧系、アイルランド系、フランス系、ドイツ系、イタリア系、ユダヤ系、東欧系等々の間で生じる潜在的な摩擦を言う。日本でも出身地や学閥が組織内で軋轢を生むことが皆無ではないが、白人でも「3代前は移民」の米国では、「血筋」は伝統や文化の違いだけでなく、祖国での歴史的な民族間抗争の怨念をも引きずっている。米国は建国以来の「理念」として、国民に出自の違いをリセットして、平等な「アメリカ人」として生きることを求めてきた。その「たてまえ」を守ろうとする社会的努力は涙ぐましいばかりだが、個人の意識の底流まで「まっさら」になっているわけではない。現政権で「たてまえ」のほころびが露呈しているのは、米国社会の「理性」(=良識=ガマン)のタガが外れかけた証拠ではないかと懸念する。タガの外れた巨大国家がどんな道を進むにせよ、「米国の尻馬に乗っていれば大丈夫」だった時代が終わったことだけは、強く認識しておくべきだろう。

ニューヨークのイメージは摩天楼、ブロードウエイ、ハーレムだろう。だが巨大都市景観はマンハッタン島とその周辺だけで、州の95%はのんびりした農村である。私は90年4月から3ヶ月間ロングアイランドに住んだ。マンハッタンから東に50kmのメルヴィルという町だが、家の前は何十町歩もある大農場で、朝早くから大型トラクターがエンジンをうならせてジャガイモを植え付けていた。この辺りからマンハッタンヘ通勤電車もあるが、新興ベッドタウンのような活気は全くない。私が住んだのは高齢の未亡人が貸間に出していた一室で、家賃は決して安くなかったが、エアコンもなく、台所やトイレの水まわりにだいぶガタがきていた。この辺りは70年代までグラマン等の防衛産業やエレクトロニクス企業が多数あるハイテク地帯だったのだが、今はすっかり寂れてしまったのだ。
 70年代にロングアイランドの通信網近代化に一役を果たしたのが、私自身も多少関与したデジタルマイクロ波通信網である(なじみの薄い読者もおられるだろうが、30年前まで電話局の屋上の鉄塔にお椀型のアンテナが乗っていたのをご記憶だろう)。マイクロ波通信の技術は戦後に米国から導入したものだが、その頃私のいた会社は既に海外市場で世界一の名声を得ていた。しかし師匠のアメリカでは売れまいと思っていたのだが、あっけなく注文がとれてしまったのだ。当時は電話をデジタル信号に変えて有線で送る技術は実用化していたが、無線で送る技術はまだ初期の段階だった。当社は有線のデジタル信号を束ねて無線で送る装置を世界に先駆けて実用化し、その記事を技術雑誌に出したところ、ニューヨーク電話会社の技術者の目に止まり、当社のニューヨーク事務所の電話を探して問い合わせてきた。東京から技術者が出張して説明することになり、海外事業の職場に異動して間も無かった私も同行することになった。1970年9月のことである。
70年代にロングアイランドの通信網近代化に一役を果たしたのが、私自身も多少関与したデジタルマイクロ波通信網である(なじみの薄い読者もおられるだろうが、30年前まで電話局の屋上の鉄塔にお椀型のアンテナが乗っていたのをご記憶だろう)。マイクロ波通信の技術は戦後に米国から導入したものだが、その頃私のいた会社は既に海外市場で世界一の名声を得ていた。しかし師匠のアメリカでは売れまいと思っていたのだが、あっけなく注文がとれてしまったのだ。当時は電話をデジタル信号に変えて有線で送る技術は実用化していたが、無線で送る技術はまだ初期の段階だった。当社は有線のデジタル信号を束ねて無線で送る装置を世界に先駆けて実用化し、その記事を技術雑誌に出したところ、ニューヨーク電話会社の技術者の目に止まり、当社のニューヨーク事務所の電話を探して問い合わせてきた。東京から技術者が出張して説明することになり、海外事業の職場に異動して間も無かった私も同行することになった。1970年9月のことである。
ブルックリンはマンハッタンからイーストリバーを渡った対岸の下町で、昨今(1994年)は旅行者は立ち入らない方が良いと言われている。70年当時は危険ではなかったが、こんなゴミゴミしたところに電話会社の技術局があるのだろうかと思うような場末だった。今思うとたどたどしいプレゼンだったが、とにかく一日がかりで説明した。帰り際に、ブルックリンと対岸のスタテン島を結ぶ回線用の機器の見積書を翌日提出するよう求められた。
当時の通信手段はテレックス(テレタイプ電信機)だった。事務所に帰り夜中までテレックスを叩いて報告と質問を送り、翌早朝に入電した資料をタイプして電話会社に出かけた。ひととおり質疑応答が終わると、「これを買う。今から調達部に行って契約手続きをしなさい」と言う。キツネにつままれたようだったが、営業役の私が一人でウォール街に近い調達部に出向いた。ブランデージさんという年輩のマネジャーが「話は聞いている」と言い、秘書にタイプを打たせて発注書が出来上がった。サインも入っている。事務所には最速交通手段 の地下鉄で帰ったが、気分は空に舞い上がっていた。花のニューヨークに和製マイクロ通信回線が立つにしては、実にあっけない幕開けだった。
この第1号機は予定どおり1971年3月に納入され、電源を入れたら何も調整しないでピタリと動いたと驚かれた。電話会社はこの機器でロングアイランドの通信網を一気に近代化する大規模な計画を立て、契約内示を出してくれた。しかし世の中はうまいことばかり続かないもので、電波使用の認可をするFCC(連邦通信局)から待ったがかかった。デジタル方式のマイクロ波通信は電波の無駄使いの疑いがあり、新ルールを作るまで認可を差し止めるというのである。日本メーカーに対するブレーキだったかどうかは分からないが、ルール作りに4年かかり、当社の方式ではダメということになった。内示で動き始めていたので損害になったが、新ルールを満たす新型装置を買ってもらうことに全力をあげた。4年の間に米国メーカーも開発を終えて競合製品を出してきたが、結局当社が採用され、その後ニューヨーク州全部のマイクロ波通信機器を全面的に受注し、他の地域の電話会社でも採用が拡大した。
試験回線として仮運用していたブルックリンの第1号機も新装置に取り替えられ、1号機は電話会社の倉庫入りしたが、78年にサンフランシスコ湾で海底ケーブルの切断事故が起きた時に、パシフィックベル電話会社に緊急用に貸し出され、ここでも電源を入れたら即稼働して驚かれ、同社との商売の糸口になった。この装置は80年のレイクプラシッド冬期オリンビックで臨時回線用に3度目の出馬をしたと聞いたが、その後どうなったのか誰も知らなかった。私がバージニアに駐在していた84年、金属回収業者を名乗る人から電話があり、妙な機械を引き取ったが当社のマークが付いている、何に使うものかと聞かれた。形状を尋ねると例の第1号機で、電話会社が屑鉄屋に出したものらしい。今の規格に合わないので商品価値はないと説明すると、2千ドルで買わないかという。私の一存で断わってしまったが、今になって思うに、ポケットマネーででも買い取っておくべき記念物だった反省している。(この項 1994年9月記、一部補足)
1970年9月以降もマンハッタンの事務所に出張して活動した時期はあったが、空港と事務所と近くの安ホテルを往来しただけで、市内観光をした記憶が無い。猛烈に働いたことも確かだが、当時の出張手当では金銭的余裕も無かった。初めてマンハッタン観光をしたのはトロント駐在が2年目に入った1980年5月で、どうしてもマトモな寿司を食べたくなり、カナダの3連休を使って家族連れで車で往復した。当時トロントに寿司屋が無かったわけではないが、口の悪い人に言わせれば「魚片乗せにぎりめし」で、あの時マンハッタンで食べた江戸前寿司の感動は今も鮮明に覚えている。次の写真の上4枚はその時に撮ったものである。 (この項 2017年9月記)
 |
|
1990年4月に2度目の米国駐在でニューヨークに赴任した。その頃は事務所がロングアイランドに移転し、マンハッタンには小生の顧客がなかったので、もっぱら「ニューヨークの田舎暮らし」だったが、それもわずか3ヶ月で切り上げ、テキサス州ダラスに移転して1995年6月まで過ごすことになる。小生はニューヨークには縁が薄かったようだ。
(この項 2017年9月記)
 |
|
1995年6月にダラス勤務を解かれて帰国し、会社勤めの最後を国内事業で過ごすことになったので、入社以来30年に及んだ米国との縁が切れた。その職場も2003年6月に退職したが、同年9月に若い社員の市場調査の手助けを頼まれ、思いがけずニューヨーク出張の機会をいただいた。以下のマンハッタンの写真は小売店舗の実態調査に同行した時のもので、会社のカネで観光したわけではない。(この項 2017年9月記)
 |
|
「パークウェイ」を辞書で引くと、「自動車専用道路」と「公園の中を走る美しい道路」の二つの意味がある。マンハッタンからジョージワシントン橋を渡り、ハドソン川西岸を北に走るパリセード・バークウェイは、この両方の意味を兼ね備えた美しいハイウェイだ。道路の両側は美しい林で、春の若葉の頃や秋の紅葉の頃に走ると、生きていて良かったなあ、と思わず感傷的になる。ハドソン河畔に下りる脇道がところどころにあり、川岸の小さな公園からゆったりした流れの向こう岸の高層アパート群や、はるか南に霞むマンハッタンの摩天楼を眺めるのも気分がよい。
ジョージワシントン橋から西に向うフリーウェイ80号線も、美しい落葉樹の林の中を走る。あちこちに工場やオフィスビルがあるが、林にまぎれ込んで点在し、日本の工業団地のような殺伐とした雰囲気はない。この地域にはATT(当時の最大手電話会社)の施設が多く、5万人を超す従業員が働いているが、古い建物も新しい施設も、羨ましいほど豊かな自然にとけこんでいる。アメリカ人は好んで「クォリティ・オブ・ライフ」というが、これは「豊かな人生」と訳すのが正しいだろう。二一ジャージーの生活は、マンハッタンの刺激の強い文化と、自然に囲まれた生活と、知的な職業と、サラリーマンとしては世界最高水準の収入が共存する、まさに「豊かな人生」の場と実感する。
ここまではニュージャージー北部の話で、南に下がると事情が違ってくる。マンハッタンの南端からハドソン川の河底トンネルをくぐってニュージャージー側に出たあたりは、精油所や石油化学工場が立ち並び、廃ガスを燃やす炎が夜も不気味に空を焼き、独特の強い匂いが漂っている。かつては石油関連だけでなく、製鉄、鉄工、機械工場が立ち並び、世界最強の力を発揮した米国重工業の中心地であった。現在でも精油所はフル操業しているが、それ以外の重工業の衰退ぶりは極めて酷いと言うしかない。ガラス窓が破れて廃墟になったビルや、ここ20年修理したことがないと思われるような破れ工場ばかりだ。マンハッタンから指呼の距離にある一等地で、日本なら地上げで再開発されただろうが、アメリカでは利益を生まなくなった廃墟はそのまま遺棄し、新しい場所で新規開発する方が理にかなっているようだ。
更に大西洋に沿って南に下がると、アトランチックシティのカジノがある。70年代、州が歳入獲得の為に地域限定でギャンブルを公認し、寂しい海水浴場に唐突にリゾートホテルが立ち並んだ。マンハッタンから直通バスが頻繁に出ているから、目当てのギャンブル客はニュージャージー定住のインテリサラリーマンではない。私は92年に何かのコンベンションで出張したが、けばけばしいホテルの周囲はのっぺらぼうな平原で、狭い海水浴場と埃っぽい土産物屋、チープな食べ物屋が点在するだけだった。目玉はニューヨークの不動産成り金が建てた豪華ホテルだったが、同氏が凋落した後はどうなったのだろうか。(注:不動産成金は25年後に大統領になった。) (この項 1994年9月記 写真ありません。)
「人民の、人民による、人民のための政治」というリンカーンの有名な演説は、南北戦争で終始押されぎみだった北軍が、1863年にゲティスバーグの戦場で大逆転を果たした時に行われたものである。今でこそリンカーンは歴代大統領の中でも最も人気が高いが、当時は必ずしも支持者は多くなかった。ゲティスバーグの勝利を機に、国家の再統一を果たそうとした気概と「力み」が、この短いメッセージに現れている。大統領自らが暗殺されたことが契機になってやっと南北戦争が終結し、再統一の気運が盛り上がったというのも、政治が持っている残酷な一面と言るだろう。
南北戦争が戦われたのは1861年から65年で、日本の幕末と同時代である。この内戦は奴隷制をめぐる南部と北部の対立と教えられたが、そういうイデオロジカルな面よりも、南北の経済戦争と見た方が実態に近いだろう。ゲティスバーグの古戦場はペンシルバニア南部の盆地にあり、今はのどかな田園地帯である。この戦場で17万人が戦ったという。今は記念公園になっているが、先ず驚かされるのは、各部隊が布陣した地点を示す1千基を越える石碑や銅像の林立である。次に驚くのは、記念碑に刻まれた部隊名と出身地から、南軍と北軍がいかに接近して入り乱れて戦ったかだ。昨今の戦争は、目に見えない敵に向かってボタンを押すテレビゲームのようになってしまい、人間を殺傷するという現実感が失われてしまった。130年前の5年間にわたる内戦では、目の前の同国人を撃ち、刺し貫き、同国人の間で70万人近い戦死者を出した。日本の幕末から維新にかけての内戦も血生臭かったが、70万人も死ぬまではやらなかった。この徹底の仕方に、アメリカ人のある種の不気味さを感じないわけにはいかない。
ゲティスバーグからさほど遠くないところにアーミッシュの集落がある。アーミッシュはスイスとドイツで発生したキリスト教の一派で、現在も徹底して機械文明を拒否する教義を頑なに守り、完全な自給自足生活を送っている。85年に当社はアパラチア山中のローリングクリークに大きな衛星地上局を建設したが、この現場への行き帰りの路上で何度もアーミッシュの馬車に出あった。一頭だての黒塗リの箱形馬車で、自動車が55マイルで頻繁に行き交うハイウェイの端をトコトコと走る。雨のタ方には見え難くて危険だが、彼等にはこれ以外の交通手段がないのだ。電話やテレビはもちろん電灯もない。子供は学校に行かせずに親が教育する。住居も仲間が寄り集まって昔からの工法で建てる。機械文明の極致にあるアメリカで世捨て人のような生活を押し通す宗教的信念は尊敬に値するが、これが押し潰されずに成り立っているのも、個人の信条に最大の価値をおくアメリカ文化の一つの表れなのだろう。 (この項 1994年9月記)
 |
|
ペンシルバニア州中部に「ステート・カレッジ」という地方都市がある。商売物の通信施設の設置場所として知ったのだが、「ペンシルバニア州立大学」(略称ペン・ステート)の所在地で、あまりにもお手軽な命名に呆れた記憶がある。その20数年後にここで学生生活を終えた娘の終了式で訪れ、「なるほど」と思った。本当に大学以外に何も無い町なのだ。(この項 2017年9月記)
 |
|
19世紀、アメリカの西進ブームのスピードが早すぎ、中西部の入り口に位置するオハイオは、最初の刺激を浴びて早熟したが、成長が途中で止まってしまったように見える。もう少し西のデトロイトやシカゴは巨大な商工業都市に発達したが、オハイオの都市はどれも育ちそこなって、広大な農地に浮んだ小さな島のようである。中学校の社会科の教科書に、大型コンバインの上を農業用小型機が飛んでいる写真があり、「アメリカの大規模な機械化農業-オハイオ州」と説明が付いていた記憶がある。
首都圏に隣り合わせながら田舎くさいのは埼玉に似ている、と言ったら埼玉に叱られるだろうが、川越に江戸の町並みが残っているように、オハイオにも19世紀のまま凍結した町があちこちにある。娘がオハイオ東南部のマリエッタという小さな町の学校に入リ、ダラスから車で二日がかりで荷物運びをしたことがある。ゆったりと流れるオハイオ川に沿って北上すると、何の産業があるのかわからない古い町が点在する。マリエッタは、フランス人がミシシッビ支流のオハイオ川を遡って入植して出来た町で、マリー・アントワネットに因んだ地名である。由緒ありそうなホテルも残っていて、ひと昔前に商工業が栄えたことがうかがえるが、今は大学だけで成り立っている町である。
町の中心部に大学キャンパスがあり、その東側の石畳のメインストリートに、煉瓦造りの古い建物を改造した商店や銀行など、人ロ1万の生活を支えるのに必要最小限のビジネスが集まっている。南と西には古い木造の住宅が並び、北側はフリーウエイのインターチェンジが出来たおかげで、小規模なモールやジャンクフード屋が並ぶ商業地になっている。東のはずれにオハイオ川に面した公園があり、船尾に大きな水かき車をつけた平底の観光船が、ゆったりと川を上下している。生き馬の目も抜くような激しい競争社会のアメリカで、時間の止まったような光景は何とも不可思議な感じがする。
アクロンには、会社がタイトルスポンサーのブロゴルフ大会が開催される「ファイアストーン・カントリークラブ」がある。この町も一時代前にタイヤ等の自動車部品産業でにぎわったのだが、今はマリエッタ同様、時間が止まった感じがしないでもない。このゴルフ大会の興業権はPGAが持っているが、主催者はアクロンの慈善団体で、会場周辺の交通整理や駐車場の案内、コースの監視員等に数千名の町民がボランティアで繰り出す。このボランティアが稼ぎ出す報酬や寄付が毎年1億円というから半端でない。この種のプロスポーツ大会はどこでも開催地の慈善収入源になっているようだ。我々から見ると、国や州の福祉政策が希薄な分を、市民や企業の善意に肩代わりさせているように見えるが、アメリカでは福祉に政府が介入するのは良くないという認識が強い。だがクリントン政権が政府介入の国民皆健康保険制度導入に政治生命を賭けているのを見ると、アメリカでも、市民や企業の善意で福祉が足りた古き良き時代は過ぎ去った、ということかもしれない。 (この項 1994年記)
 |
|